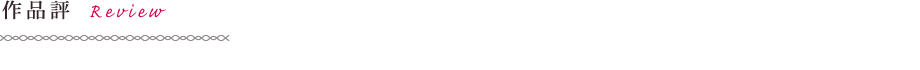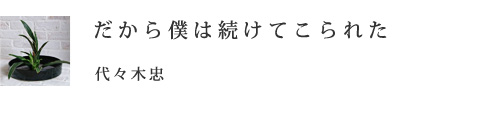この映画を褒めるのは、どこか自分を褒めるようで言いづらい面もあるが、この作品が石岡監督の労作であることは間違いない。僕自身もこういうふうに客観的に見せられると、波乱万丈ではあるけれど、ツイているといえばツイている人生だと思える。そんななか、劇中で流れる自分の作品の数々を見ながら、ひとつの疑問が湧き上がってきた。
なんで僕はこういう作品ばかり撮りつづけてきたんだろう?
こんな難しい方向に来なくても、もっと娯楽作品としての抜きビデオだけを撮ればよかったのに・・・。抜きと割り切って、それに徹することができれば、それはそれで凄いことだと思う。ところが、僕はそっちに行き切れなかった。言い方を換えれば、どっかでいい恰好をしている自分がおり、そんな自分を捨てられなかったのだ。でも、なぜ捨てられなかったんだろう?
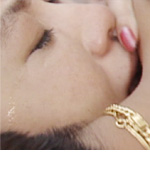
ビデオに出演した女の子がこれまでの人生で負った心の傷と、僕の中のある部分が共鳴し、それによって僕自身が癒されたというのは確かにある。だから、この一本道を、どこに行き着くのかも考えずに、ただただ進んできたのだと。だが、それだけじゃあない。結局、僕は自分の娘たちに軽蔑されたくなかったのではないだろうか。親とのつながりにおいて不幸だった女の子たちを、僕はたくさん見てきた。思春期の学びや体験は、のちのちの人生に大きな影響を与える。なによりも父親である僕を信じられないというのが怖いと思った。なぜなら、娘たちにとって父親は最初の異性であるからだ。父親が信じられないというのは、男を信じられないことにつながる。男を信じられない女の人生が幸福だとはとても思えない。実際、僕はそういう女の子たちと現場でたくさんふれあってきたのだった。
娘たちが思春期になったとき、もしも僕の作品をどこかで見たとしても、彼女たちが僕を信じられなくなってしまわないためには・・・。女の股ぐらでメシを食わせてもらっているという後ろめたさは僕の中で完全には消えずとも、その反面というか、だからこそというか、胸を張って娘にも語れる、自分の信念みたいなものを作品の中に溶かし込みたい。そして、出演した女の子ばかりでなく、見てくれた人にも、セックスを通してどうしたら人は幸せになれるのかについて、僕なりにつかんだ何かを示せないものか・・・。

ただそれは作品づくりだけではなく、日常、家庭の中でも娘たちには嘘をつかず、本音でつきあってきた自負がある。余談になるが、これは女房にも同様で、これまでさんざん自分をさらけ出し合ってきた。それを言ったらお終いだよということまで、お互いが罵り合ってきた。大喧嘩した翌朝、顔を合わせるときには、さて、どう切り出したものかと僕はちょっと悩むのだが、女房のほうは昨夜さんざん吐き出してしまったからか、「おはよう!」とふつうに声をかけてくる。何事もなかったかのようにケロッとしているのである。女房と娘がやり合うところも凄まじい。女同士の親子バトルは、ある意味、夫婦よりも激しいのだ。僕はそれを端で見ていて、こりゃあ2、3日大変だなぁと、心の準備をしておくことにする。ところが、2、3時間後には、「ねぇ、お母さん、祖師谷温泉に行かなぁい?」などと娘が言っている。えええ、なんでそんなこと、ふつうに言えるんだよ・・・と内心舌を巻きつつ、血は争えないと思う。
娘たちがいたから、守るべき家族があったから、僕は続けてこられたに違いない。試写会後、僕はそんなことを考えていた。
(アテナ映像公式HP内のブログ「週刊代々木忠」より)